令和6年度住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について
住民税非課税世帯支援給付金(1世帯3万円給付)について
令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策に基づき、令和6年度において住民税非課税となる世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、支給対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき2万円を加算します(子ども加算給付金)。
支給対象世帯に対し、支給通知もしくは確認書(申請書類)を福祉課から送付します。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
支給対象者
以下の(1)~(2)に該当する世帯の世帯主
(1)基準日(令和6(2024)年12月13日)に肝付町の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)世帯員全員が令和6年度の住民税均等割が課税されていない世帯
(候補↓)
- 基準日(2024年12月13日)において肝付町の住民基本台帳に記載されている世帯であること
- 世帯の全員が2024年度住民税非課税であること
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
- 肝付町以外の自治体において、同給付金を受給していないこと
支給対象外
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている世帯
・「親元からの扶養を受けるひとり暮らしの大学生」、「別世帯の子からの扶養を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする世帯」、「令和5年中は親の扶養を受けていた令和6年度からの新社会人」の方等は、特にご注意ください。
・世帯全員が、専従者である世帯
・住民税が、未申告の方がいる世帯 ※18歳以下の児童は除く
・住民税の申告内容を変更し、給付金の対象外になった世帯
・租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
・令和6年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯
・他の市区町村で、低所得者世帯支援給付金と同等の給付金の支給対象となった世帯
支給額
・1世帯あたり3万円
・支給対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子ども1人あたり2万円加算
支給手続等
支給方法は、「プッシュ支給【支給通知書を送付 】」と「申請による支給【申請書(請求書)を送付】」の2種類になります。
(1)プッシュ支給【支給通知書を送付 】
発送対象世帯
肝付町において令和6年度の住民税が非課税であることが確認できる世帯
支給通知書発送時期
令和7年2月28日(金曜日)
手続方法
【支給口座欄へ「口座の記載」がある方】
給付金受取口座の登録がされている方になります。口座に変更がなければ、手続きの必要はありません。
【支給口座欄が「空白」である方】
給付金受取口座の登録が登録されていない方になります。口座の届出が必要になります。
口座の登録(変更)をご希望の方は、通知書の下記「■口座の登録(変更)したい方は・・・」をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえて福祉課までご提出ください。(申請書受理後1〜2週間後の支給になります。)
手続期間
【既に口座の登録がある方】
振込口座変更・辞退受付期間 令和7年3月14日(金曜日)まで
振込時期 3月21日(金曜日)※口座の登録(変更)をされた方については申請書受理後1〜2週間後の支給になります。
【口座の登録がない方】
振込口座新規登録受付期間 令和7年5月31日(当日消印有効)
※申請書受理後1〜2週間後の支給になります。
(2)申請による支給【申請書(請求書)を送付】
発送対象世帯
発送対象世帯 令和6(2024)年1月1日から基準日までの間に住民票の世帯変更や税の修正申告等をした世帯、転入等により税情報が確認できない世帯等
申請書(請求書)発送時期
令和7年2月28日(金曜日)
手続方法
申請書(請求書)が届き次第、内容をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえ、同封の返信用封筒にて提出してください。
提出が必要な書類
1.住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)
2.申請・請求者本人の公的身分証明書のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書、パスポート等
3.受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカード等
4.住民税課税証明書または住民税非課税証明書(現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分)
手続期間
受付期間 令和7年5月31日(当日消印有効)
振込時期 申請書受理後1〜2週間後の支給になります。
※返送された確認書に不備がある場合、修正などの手続きが必要となるため、振込時期が遅くなる場合があります。
(3)子ども加算給付金について
・上記給付金に該当する世帯のうち、18歳以下の(平成18年4月2日以降に生まれた)子どもがいる世帯へ子ども1人あたり2万円加算給付します。
・こども加算給付金については原則申請不要です支給通知書に記載のある金額の確認をお願いします。(本体給付金3万+子ども1人あたり2万)
・こども加算給付金は、同じ口座への振込となります。
ただし、以下の対象者については「支給通知」または「確認書」に記載していない場合があるため、該当する場合は申請が必要になります。
令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年5月31日までに生まれた新生児
令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年5月31日までに生まれた新生児のこども加算給付金については、追加での支給となります。申請によりこども加算給付金の対象となる場合がありますので、該当する場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
別世帯だが、扶養している18歳以下の子ども
令和6年12月13日(基準日)時点で、単身で学校の寮に入っているなど、支給対象者(世帯主)とは別世帯だが、扶養している18歳以下の児童がいる場合、申請によりこども加算給付金の対象となる場合がありますので、該当する場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
その他
・住民税非課税世帯支援給付金の支給には、町県民税の課税情報を確認する必要があるため、令和6(2024)年度の町県民税が未申告の世帯員がいる世帯については、申告を行うことで支給を受けられる可能性があります。未申告の世帯員がいる世帯については、税務課で申告を行ってください。
・肝付町が申請書等を受領したのち、申請書等に不備があり修正を求めたにもかかわらず、受付期間までに町に修正の提出や連絡ができない場合は、給付金の受給を辞退したものとして取り扱います。
・肝付町が支給決定した後、振込口座を解約・変更したなどの事由により支払いが完了せず、受付期間までに町が連絡・確認できない場合は、給付金の受給を辞退したものとして取り扱います。
・肝付町住民税非課税世帯支援給付金の支給を受けた後に、町県民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により肝付町住民税非課税世帯支援給付金の支給を受けた場合は、支給済みの給付金を返還していただくことがあります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
自宅などに給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
市区町村や総務省などが以下を行うことは絶対にありませんので注意してください。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 給付のための手数料などの振込を求めること
- 銀行口座の暗証番号を照会すること
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 福祉推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
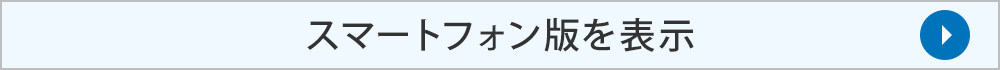






更新日:2025年02月28日