帯状疱疹予防接種の費用助成(定期接種・任意接種)
肝付町では、50歳以上の方を対象に帯状疱疹予防接種を行った際の接種費用の一部助成を行います。
帯状疱疹予防接種は定期接種と任意接種の2種類があり、年齢によって異なります。

定期予防接種について
対象者
接種日時点で肝付町に住所があり
過去に助成制度を利用して帯状疱疹予防接種を受けたことがない
令和8年3月31日時点で下記の年齢の方
- 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳(※)
※100歳以上の方については令和7年度に限り全員対象です。
- 60歳〜64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
助成金額
4月中に町から届く予診票を使用して、医療機関の設定した接種費用から助成額を差し引いた金額を医療機関へ支払ってください。
- 生ワクチン:上限4,000円を1回助成
- 不活化ワクチン:上限10,000円を2回助成
接種場所
事前にお電話等で予約をお願いします。
任意予防接種について
対象者
接種日時点で肝付町に住所があり
過去に助成制度を利用して帯状疱疹予防接種を受けたことがない
満50歳以上の方で定期接種対象外の方
助成金額
医療機関では、一旦全額自己負担となりますが、接種後に申請を行っていただくことで助成金を振り込みます。
- 生ワクチン:上限4,000円を1回助成
- 不活化ワクチン:上限10,000円を2回助成
※不活化ワクチンは1回目と2回目の接種間隔が6ヶ月を超えた場合は、助成の対象となりません。
医療機関
帯状疱疹の予防接種を実施しているか医療機関に確認し、予約の上、予防接種をうけてください。
申請に必要なもの
・予防接種の支払いを証明するもの(原本)※原本を確認後、コピーをとり原本は返却します。
・帯状疱疹の予防接種を受けたと分かる書類(診療明細書・予診票等)
・振込を希望する預金通帳
・印鑑
上記書類を役場に持参のうえ、申請書に必要事項を記入していただきます。
接種日から1年以内に申請してください。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、多くの人が子どものときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で発症します。水ぼうそうが治った後もウイルスは体内に潜伏しており、加齢などで免疫力が低下しやすい50歳からはとくに発症しやすく、70歳代が最も発症率が多くなっています。
主な症状は、体の一部にピリピリとした痛みがあらわれ、その部分に赤い発疹が出ます。症状の多くは上半身にあらわれ、顔や目、頭などにあらわれることもあります。
帯状疱疹ワクチンについて
帯状疱疹のワクチンは、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類あります。接種にあたり医師と相談し、どちらかのワクチンの予防接種をうけてください。
|
【生ワクチン】 乾燥弱毒生水痘ワクチン |
【不活化ワクチン】 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
|
| 接種回数 | 1回 | 2ヶ月以上の間隔を置いて2回 |
| 接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
| 接種条件 |
病気や治療によって、免疫の 低下している方は接種できません |
免疫の状態かかわらず接種可能 |
ワクチンの予防効果
|
【生ワクチン】 乾燥弱毒生水痘ワクチン |
【不活化ワクチン】 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
|
| 接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
| 接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
| 接種後10年時点 | ー | 7割程度の予防効果 |
ワクチンの安全性
- ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
- 頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
|
主な副反応の発現割合 |
【生ワクチン】 乾燥弱毒生水痘ワクチン |
【不活化ワクチン】 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
| 70%以上 | ー | 疼痛※ |
| 30%以上 | 発赤※ | 発赤※、筋肉痛、疲労 |
| 10%以上 | そう痒感※、熱感※、腫脹※、疼痛※、硬結※ | 頭痛、腫脹※、悪寒、発熱、胃腸症状 |
| 1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感※、倦怠感、その他の疼痛 |
(※)ワクチンを接種した部位の症状
他のワクチンとの同時接種について
-
帯状疱疹ワクチンは、医師が特に必要と認めた場合に、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等と同時接種が可能です。
-
生ワクチンは、他の生ワクチンと27日以上の間隔をおいて接種してください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課 健康増進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2564
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
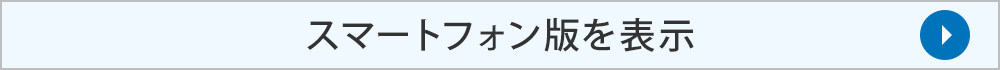






更新日:2025年04月07日