よくある質問(Q&A) 定額減税を補足する給付金(不足額給付)
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について、よくある質問を掲載しています。不足額給付の制度の概要等については、「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)」のページをご確認ください。
1.基本
Q1-3.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されますか。
2.対象について
Q2-1.令和7年度住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。
Q2-2.令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなるのでしょうか。
Q2-3.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか。
Q2-4.昨年の8月以降に支給された調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
Q2-5.令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていたが、就職して令和6年分所得税が課税された。不足額給付の対象になりますか。
3.申請について
4.給付について
Q4-1.令和6年中に扶養していた親族が転出により減りました。給付額は変わりますか。
Q4-2.令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
Q4-3.令和6年中に子供が生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
Q4-4.令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか。
5.その他
Q5-2.給付を受ける口座を変更したい場合はどうすればいいですか。
Q5-3.給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告をする必要はありますか。
Q5-4.確定申告をするとき、確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか?
1.基本
Q1-1.不足額給付とは
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
1.調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
2. 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
詳しくは「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)」をご確認ください。
Q1-2.私は不足額給付の対象になりますか
不足額給付の対象となる方には、令和7年9月以降、「支給のお知らせ」、「確認書」または「申請書」を送付予定です。
ただし、給付対象者であっても、肝付町からのご案内が届かない場合もあります。
10月になっても届かない場合は、ウェブページ等に掲載の方法で申請してください。
Q1-3.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されますか
控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に調整給付金を支給しています。
不足額給付金は調整給付金を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。
2.対象について
Q2-1.令和7年度住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか
令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている人であっても、次の例に該当する場合は不足額給付の対象となります。
1 令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
2 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
(注)住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。
(注)例に示した以外に、事業専従者や合計所得金額48万円超の方の内、条件を満たす方は不足額給付の対象となります。
Q2-2.令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなるのでしょうか
こどもが生まれることなどの扶養親族の数が増えたことにより、令和6年8月以降に肝付町から支給された当初給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。
Q2-3.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか。
【不足額給付II】の対象となる可能性があります。
Q2-4.昨年の8月以降に支給された調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
不足額給付の対象要件を満たしていれば、(給付対象外で当初調整給付を受給していなかったとしても、)不足額給付を受給することができます。
ただし、当初調整給付の受給対象であったが受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
Q2-5.令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていたが、就職して令和6年分所得税が課税された。不足額給付の対象になりますか。
令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。
3.申請について
Q3-1.不足額給付を受けるために、申請は必要ですか。
【不足額給付I】
・「支給のお知らせ」が届いた方は、原則申請不要です。
・「確認書」が届いた方は、申請が必要です。
【不足額給付II】
・支給要件の確認が必要なため、原則本人からの申請が必要です。肝付町で確認ができる方については、「支給のお知らせ」・「確認書」または「申請書」を送付いたします。
4.給付について
Q4-1.令和6年中に扶養していた親族が転出により減っている。給付額は変わりますか。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人減っているのであれば、令和6年度個人住民税における減税対象人数より1名分少なくなります。
(※)不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付を下回った場合は、余剰額の返還は求めません。
Q4-2.令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。
Q4-3.令和6年中に子供が生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
令和6年中に子どもが生まれた等、扶養親族の数が増えたことにより、令和6年に実施された「当初調整給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
(注)個人住民税の定額減税額は令和6年12月31日時点の扶養親族数に基づいて算定されます。令和6年中の扶養親族数の変更があったとしても、個人住民税の定額減税額には影響しません。
Q4-4.令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか。
不足額給付の対象にはなりません。
(注)令和6年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
5.その他
Q5-1.受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象とはなりません。
Q5-2.給付を受ける口座を変更したい場合はどうすればいいですか。
「支給のお知らせ」に記載している口座情報は、町が保有する口座情報や、公金受取口座の情報をもとに登録しています。
別の口座をご希望でしたら、「支給のお知らせ」に記載している問い合わせ先までご連絡いただくかオンライン申請してください。町にて口座情報を保有していない場合には、「確認書」を送付させていただきます。
オンライン申請については、【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)についてをご覧ください。
Q5-3.給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告をする必要はありますか。
給与収入と公的年金収入で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行う必要はありません。このため、従来通り、下記の事項に該当する方については、確定申告をする必要はありません。
給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方(※)
(※)その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている方に限ります。
Q5-4.確定申告をするとき、確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか?
確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては、「国税庁ホームページ【申告が間違っていた場合】」をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
メールフォームによるお問い合わせ
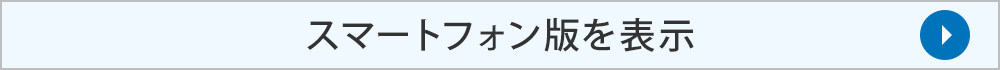






更新日:2025年09月08日