「南海トラフ地震臨時情報」発表時における肝付町の対応について
令和元年5月31日から、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合に、気象庁による「南海トラフ地震臨時情報」が発表されることとなり、肝付町でも南海トラフ地震防災対策推進計画を改正し運用を開始しました。
◆南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合等に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されます。
◆政府や地方公共団体(肝付町)などからの呼びかけ等に応じた防災対応をとりましょう。
◎南海トラフ地震とは
南海トラフ地震は、静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、概ね100~150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震です。
前回の南海トラフ地震(昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年))が発生してからすでに70年以上が経過しているため、今後30年以内の発生確率は70~80%とされており、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっています。

出典:南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応(内閣府「防災情報のページ」)
過去に発生した南海トラフ地震では、マグニチュード8クラスの大規模地震が時間差で発生した事例があります。
安政東海地震の際には、32時間後に安政南海地震が発生し、昭和東南海地震の際には、2年後に昭和南海地震が発生しています。南海トラフの東側で大規模地震が発生した後に、時間差で西側でも大規模地震が発生する可能性が高いということになります。
◎南海トラフ地震臨時情報とは
南海トラフ付近でM6.8程度以上の地震が発生した場合やプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合、国が調査を開始するとともに、気象庁が「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を発表します。
国の行う調査・分析の結果により、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」、「南海トラフ地震臨時情報(調査終了)」のいずれかが発表されます。
情報ごとの発表条件は次のとおりです。
| キーワード | 発表条件 |
| [調査中] | 観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、又は調査を継続している場合 |
| [巨大地震警戒] | 巨大地震の発生に警戒が必要な場合 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生したと評価した場合 |
| [巨大地震注意] | 巨大地震の発生に注意が必要な場合 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上M8.0未満の地震や通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合等 |
| [調査終了] |
[巨大地震警戒][巨大地震注意]のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合 |
◎南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応
発表される臨時情報の種類によって、町民の皆様の対応も異なります。
「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたときは、国や気象庁、町などの発する情報や呼びかけ等に応じた防災対応をとってください。
どの種類の臨時情報であっても、まずは、「自宅周辺の危険箇所等の確認」、「避難場所・避難経路の確認」、「家族との連絡手段の確認」、「家具の転倒防止」、「高いところに置いてある品物の撤去」、「非常持出品の準備」など、日頃からの地震への備えを再確認してください。
臨時情報ごとの防災対応の概要は、次のようになります。
1.南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)
(1)発表後から1週間
・日頃からの地震への備えを再確認する。
・津波からの避難が間に合わない一部の地域の高齢者等避難に時間を要する町民(要 配慮者)は、避難を開始する。(1週間を目途に避難行動を実施)
・上記以外の町民は、個々の状況等に応じて自主避難を開始する。(1週間を目途に自主避難を実施)
(2)1週間後
・避難を解除する。
・日頃からの地震への備えを再確認する等、1週間地震に備える。
(3)2週間後
・地震の発生に注意しながら通常の生活を送る。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意する。
2.南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)
(1)発表後から1週間
・日頃からの地震への備えを再確認する。
(2)1週間後
・地震の発生に注意しながら通常の生活を送る。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意する。
(3)2週間後
・2週間後も、地震の発生に注意しながら通常の生活を送る。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意する。
3.南海トラフ地震臨時情報(調査終了)
・地震の発生に注意しながら通常の生活を送る。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意する。
南海トラフの想定震源域やその周辺等でM 6.8以上の地震等が発生した場合の防災対応の流れを、臨時情報の種類ごとにフロー図にまとめると、次のようになります。

◎地震への備えの再確認やとるべき行動のチェックリスト
フロー図の≪地震発生後の防災対応の流れ≫にある「日頃からの地震への備えを再確認する等」とは、「自宅周辺の危険箇所等の確認」、「避難場所・避難経路の確認」、「家族との連絡手段の確認」、「家具の転倒防止」、「高いところに置いてある品物の撤去」、「非常持出品の準備」などの再確認のことになりますが、詳しくは、末尾の「地震への備えの再確認やとるべき行動のチェックリスト」に基づいて再確認していただくことになります。
◎高齢者等事前避難対象地域の指定
肝付町の「南海トラフ地震防災対策推進計画」では、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合の「津波からの避難が間に合わない一部の地域では1週間避難を継続」する必要のある地域(高齢者等事前避難対象地域)として、内之浦地区の次の2地域を指定しました。
・樫脇(北方) ・小野(南方)
指定にあたっては、肝付町の津波浸水想定区域内に住居等がある地域について、緊急避難場所等までの距離や避難時間、周囲の危険箇所等を考慮して検討しました。
指定した2地域の高齢者等避難に時間を要する方々(要配慮者)は、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合には、町の発する情報(「避難準備・高齢者等避難開始」等の情報)に基づいて事前避難していただくことになります。指定した2地域の要配慮者以外の方々も、個々の状況に応じて事前避難が必要な場合は、自主避難していただくことになります。
避難先としては、知人宅や親類宅等を基本としますが、避難所に避難される方も多いと予想されますので、「上北地区研修センター」、「高山やぶさめ館」、「肝付町福祉会館」の3か所を、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合の避難所として指定しました。
◎南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時の防災情報等
南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、時間経過とともに防災対応が変化します。臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、フロー図の≪地震発生後の防災対応の流れ≫にあるとおり、後発地震に備えて特に警戒を強めた防災対応をとっていただくことになります。
臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の防災情報等の流れをイメージすると下図のようになります。フロー図と併せて参考にしてください。

◎町が管理する施設における南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時の対応
今回改正した「肝付町南海トラフ地震防災対策推進計画(以下、「本計画」という。)」では、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された際の、町が管理する施設等における管理上の措置及び体制をおおむね次のとおり定めました。
町が管理する施設等とは、町が管理する道路、河川、海岸、漁港施設、庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、病院、学校等が該当します。
1 各施設に共通する事項
(1)臨時情報(巨大地震警戒)等の入場者への伝達
ア.入場者等が極めて多数の場合は、これらの者が南海トラフ地震臨時情報(巨大地震 警 戒)等の発表された際、とるべき防災行動をとり得るよう適切な伝達方法を事前に検討しておく。
イ.避難場所や避難経路、避難対象地域、交通対策状況その他必要な情報を併せて伝達するよう事前に検討しておく。
(2)入場者等の安全確保のための避難等の措置
(3)施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置
(4)出火防止措置
(5)水、食料等の備蓄
(6)消防用設備の点検、整備
(7)非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情報を入手するための機器の整備
(8)各施設における緊急点検、巡視
ア.緊急点検の実施必要箇所は、各施設で事前に取り決めておく。
イ.巡視は、各施設の管理者等の責任で定期的に行う。
(9)上記(1)~(8)における実施体制等については、施設ごとに事前検討したうえで定めておく。
2 個別事項
(1)橋梁、トンネル、道路
大規模地震発表時に備えた施設管理上の措置を事前に検討し、定めておく。
(2)河川、海岸、漁港施設
水門及び閘門の閉鎖手順の確認又は閉鎖等津波の発生に備えて講じるべき措置を事 前に検討し、定めておく。
(3)病院
ア.患者等の保護等の方法を事前に検討して定めておく。
イ.南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時に備えた初動訓練の実施。
(4)学校
ア.児童生徒等に対する保護の方法を事前に検討して定めておく。
イ.南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時に備えた初動訓練の実施。
(5)社会福祉施設
ア.入所者の保護及び保護者への引き継ぎの方法を事前に検討して定めておく。
イ.南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時に備えた初動訓練の実施。
※病院、学校、社会福祉施設については、今後、説明会や講習会等の場を設けて本計画の周知を図り、南海トラフ地震臨時情報が発表された際の防災対応を定めていただく予定です。
☆地震への備えの再確認やとるべき行動のチェックリスト
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 消防交通係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
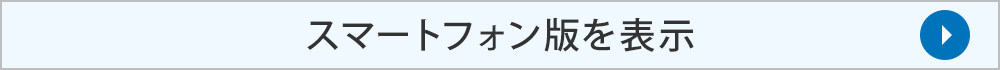






更新日:2024年08月08日