出産育児一時金
国保の被保険者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
(死産や流産等でも支給対象になる場合がありますのでお問い合わせ下さい。)
申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
◎国保の加入期間が6ヶ月未満で、国保加入以前に職場などの健康保険の加入期間が1年以上ある方は出産育児一時金の支給対象となりません。
※勤務先等の健康保険での手続きになりますので、そちらにお問い合せください。
◎産科医療補償制度(通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能を併せ持つ制度)に加入・未加入、在胎週数22週以降・22週未満の違いにより、出産育児一時金の額が下表のように定められています。
出産育児一時金の額
| 出 産 時 期 | 金 額 | |
|---|---|---|
|
産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合 |
50万円 | |
|
同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、 同制度に未加入の医療機関で出産した場合 |
48万8千円 | |
支払方法
出産育児一時金直接支払制度の場合
出産育児一時金を出産費用として直接医療機関へ支払う制度で、役場窓口で申請する必要はありません。出産費用が上記の額を上回った場合、退院時に差額のみを支払い、下回った場合、申請により差額を支給します。
なお、この制度を利用するには出産前に世帯主と出産予定の医療機関が合意文書を締結する必要があります。
直接請求の場合
役場窓口で申請することで出産育児一時金を支給します。
※差額支給及び直接請求は原則口座振込となります。保険税の納付が滞っている世帯に限り、窓口支給を行い、出産育児一時金の一部を納税していただくことがあります。
|
支給申請に必要なもの |
●出産された方の国保の資格が確認できるもの ●出産を証明するもの (母子健康手帳、出生証明書等) ※死産・流産の場合は医師の証明書 ●世帯主名義の通帳(口座確認のため) ●医療機関との直接支払いの合意文書、領収書等 |
|---|
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
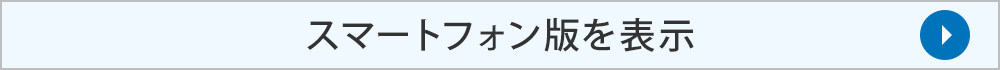






更新日:2024年12月06日